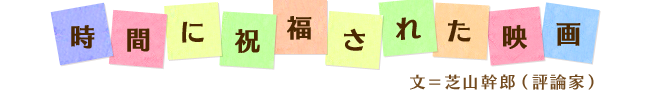
稀有な映画だ。
発想が稀有なだけではない。プロセスが稀有で、果実がさらに稀有だ。だが、鬼面人を驚かせる奇抜な印象はない。むしろ、水面は静かだ。おだやかな波が岸辺を洗い、何事もなかったかのように引いていく。
にもかかわらず、水中の深いところではなにかとんでもないことが起きている。いや、その動きはほとんど感知できない。ということは、とんでもない実験や冒険、あるいはとんでもないギャンブルが、音もなく試みられている、と言い換えたほうが適切なのかもしれない。さすがはリンクレイター、やはり只者ではなかったか。
こうつぶやきながら、私は『6才のボクが、大人になるまで』に引き込まれていった。
2002年、リチャード・リンクレイターは、メイソン(エラー・コルトレーン)という少年を主人公にした映画を撮りはじめた。原題はBoyhood(少年期)。ドキュメンタリーやホーム・ムービーではなく、れっきとした劇映画だ。ただし、撮り方が尋常ではない。リンクレイターは、6歳のメイソンが18歳になるまでの12年間を、同じ俳優とほぼ同じスタッフを使って、継ぎ目なしに撮ろうとしたのだ。
 ひとりの人物を追いかけた映画は、これまでにもいくつかある。たとえば、フランソワ・トリュフォーは、『大人は判ってくれない』(59)、『アントワーヌとコレット/二十歳の恋』(62。オムニバス映画の1篇)、『夜霧の恋人たち』(68)、『家庭』(70)、『逃げ去る恋』(79)と断続的に連なる5本の映画を通して、主人公アントワーヌ・ドワネル(ジャン=ピエールレオ)の20年間を描いた。13歳の繊細な少年だった彼は、成人したあと、どんな愛に出会い、どんな風に傷つき、どう生きていったのか。このシリーズが、リンクレイターの代表作として評価の高い〈ビフォア3部作〉の母胎となっていることは、ここで付け加えるまでもないだろう。あるいは、イギリスのグラナダ・テレビが制作したドキュメンタリー番組『セヴン・アップ』を思い出してもよい。これは、1964年に英国各地から7歳の子供たち14人を選び出して7年おきにインタヴューし、その変貌を追跡した作品だ。『セヴン・アップ』のつぎは『7プラス・セヴン』。以下、『21アップ』、『28アップ』とつづいて、現在は『56アップ』までが放送されている。
ひとりの人物を追いかけた映画は、これまでにもいくつかある。たとえば、フランソワ・トリュフォーは、『大人は判ってくれない』(59)、『アントワーヌとコレット/二十歳の恋』(62。オムニバス映画の1篇)、『夜霧の恋人たち』(68)、『家庭』(70)、『逃げ去る恋』(79)と断続的に連なる5本の映画を通して、主人公アントワーヌ・ドワネル(ジャン=ピエールレオ)の20年間を描いた。13歳の繊細な少年だった彼は、成人したあと、どんな愛に出会い、どんな風に傷つき、どう生きていったのか。このシリーズが、リンクレイターの代表作として評価の高い〈ビフォア3部作〉の母胎となっていることは、ここで付け加えるまでもないだろう。あるいは、イギリスのグラナダ・テレビが制作したドキュメンタリー番組『セヴン・アップ』を思い出してもよい。これは、1964年に英国各地から7歳の子供たち14人を選び出して7年おきにインタヴューし、その変貌を追跡した作品だ。『セヴン・アップ』のつぎは『7プラス・セヴン』。以下、『21アップ』、『28アップ』とつづいて、現在は『56アップ』までが放送されている。
両者に共通するのは、撮影の間隔が長いことだ。トリュフォーは20年かけて5本の映画を撮った。『アップ』シリーズに一貫して関わってきたマイケル・アプテッドも、「7年おき」という撮影ペースは崩していない。
しかしリンクレイターは、「12年間、毎年夏に撮影して1本の劇映画を完成させる」という冒険に挑んだ。ドキュメンタリーなら、バスケットボールの選手をめざすふたりの少年を6年間にわたって追いつづけた『フープ・ドリームス』という作品があるが、こんな手法を選んだ劇映画は寡聞にして知らない。もしかすると、映画史上初めての冒険か。
メイソンには家族がいる。母パトリシア・アークエット)と姉(ローレライ・リンクレイター。監督の長女)がいて、別居中の父(イーサン・ホーク)ともしばしば顔を合わせる。環境はもちろん変化するのだが、彼らの間柄は基本的には変わらない。
しかし、と私は問いを重ねたくなる。映画の撮影で、そんなことが可能なのか。12年もの間、同じキャストやスタッフが、1本の映画のために集まってくれるのか。怪我や病気や死亡といった不慮の事故は起こらないのか。心変わりした少年や少女が「もういやだ」と駄々をこねることはないのか。製作費はつづくのか。そもそもリンクレイター自身が、心身の健康を維持できるのか。 「ギャンブル」という言葉を使ったのはそのためだ。1年に3日か4日とはいえ、全員が万難を排して同じ場所に集まり、1本の映画のために力を合わせる。献身的な作業と書きかけて、これは「献身」そのものだと私は思い直した。だが、献身が美談にのみ結びつくとは限らない。失望や内紛や解体や破滅は、すぐそばで口をあけている。
「ギャンブル」という言葉を使ったのはそのためだ。1年に3日か4日とはいえ、全員が万難を排して同じ場所に集まり、1本の映画のために力を合わせる。献身的な作業と書きかけて、これは「献身」そのものだと私は思い直した。だが、献身が美談にのみ結びつくとは限らない。失望や内紛や解体や破滅は、すぐそばで口をあけている。
リンクレイターは、このリスクを厭わなかった。私は撮影現場を見ていないが、映画を注意深く見れば、時間の経過は手に取るようにわかる。日付の字幕も必要ない。通常ならば技巧を弄して(俳優を変えるとかメイクアップを凝らすとか)作り上げられる「加齢」や「生成変化」が、ここでは文字どおり体現されている。少年の顎の曲線が鋭角的になり、眉が濃くなり、丸みを帯びた腹部が平らになり、細かった腕がたくましくなっていく微妙な変化は、CGとはかなりちがう。
もちろんリンクレイターは、母や父や姉の肉体的な変化、彼らが体験する環境の変化もつぶさにとらえる。とくに眼を奪うのは、自身の判断ミスと運の悪さが原因でいろいろと難儀する母親の姿だ。パトリシア・アークエットは(ほとんどあからさまに)体型と表情を変え、この役に忘れがたい輪郭を与える。
キャメラがとらえるのは、肉体の変化だけではない。21世紀初頭の12年間とあって、服装や髪型に極端な変化は見られないが、それでも街並みは変化するし、「その時期にしかなかったもの」の痕跡も随所に認められる。コールドプレイの演奏する『イエロー』。マイクロソフトのX-BOX。ヒューストン・アストロズのユニフォームを着た43歳のロジャー・クレメンスや、2005年だけとくに活躍した外野手のジェイソン・レイン。

父親が大切にするヴィンテージ物の黒いGTOだけは時代を超えているが(モンテ・ヘルマン監督の『断絶』に出てくるあの車だ)、楔のように点描される背景は、「流れる時間」を実感させてくれる。いや、はっきりとした記号だけではない。メイソンが自転車を走らせる住宅地や、父と子が一緒に泳ぐ天然のプールといったありきたりの風景も、メイソンが育つテキサスという空間をさりげなく示す。そう、登場人物の肉体の変化と風景の変化が無理なく手を結べば、観客の心はゆっくりとほぐれはじめる。リンクレイター得意の、弱火で素材を煮込む調理法だ。言い換えれば、意図的なスローバーン。 私は知らず知らず、身を乗り出していた。メイソンが笑うと、なぜ私も笑いたくなるのだろう。メイソンがくじけると、なぜ私もくじけたような気分になるのだろう。メイソンを演じる役者の演技を、というより、幼時から親しかった子供が成長していく姿を見ているような気になるのはなぜだろうか。
いうまでもないが、リンクレイターはこの映画からメロドラマの要素を極力排除している。余計な昂揚や感傷の強調が観客を白けさせることを彼は熟知している。ドラマがあろうがなかろうが、人生は飛び去る。人生は苦しく、たまに美しい。人生はもろい。別れた人たちすべての行く末を見届けることなど、われわれにはできない。
だからこそ、リンクレイターは人生の一瞬一瞬を抱きしめる。ひとつの家庭を描いて、数百万の家庭を浮き彫りにする。人間が「感じる動物」であることも、さりげなく伝える。すると、時間が映画の味方をする。映画が時間を味方につけるというよりも、時間が映画の味方になり、祝福さえ与えてくれるのだ。静かな奇跡が、私の眼の前で起こっていた。
芝山 幹郎(しばやま みきお)
<略歴>
1948年、金沢市出身、東京大学仏文科卒。翻訳家、評論家。
「週刊文春」シネマチャートの評者を25年以上務めている。著書に「映画は待ってくれる」(中央公論社)「アメリカ映画風雲録」(朝日新聞出版)「映画一日一本」(朝日文庫)等。訳書にスティーヴン・キング「不眠症」「ニードフル・シングス」(共に文春文庫)最新著作は「今日も元気だ映画を見よう」(角川SSC新書)